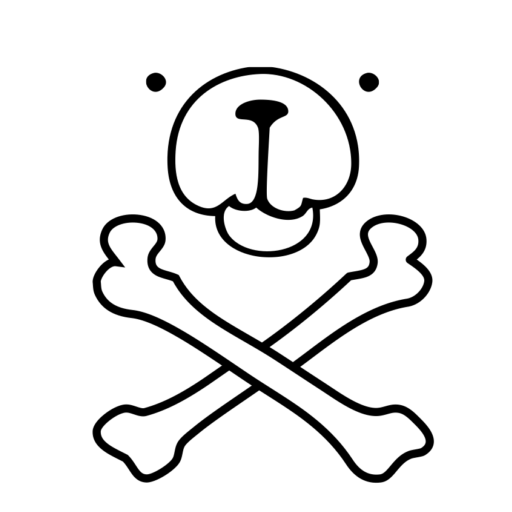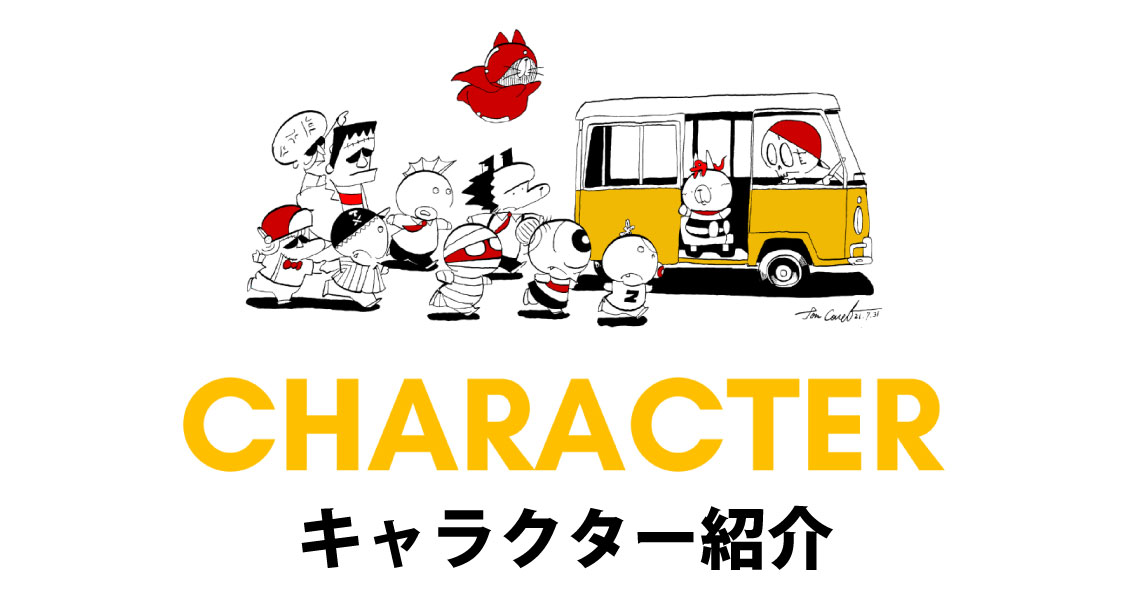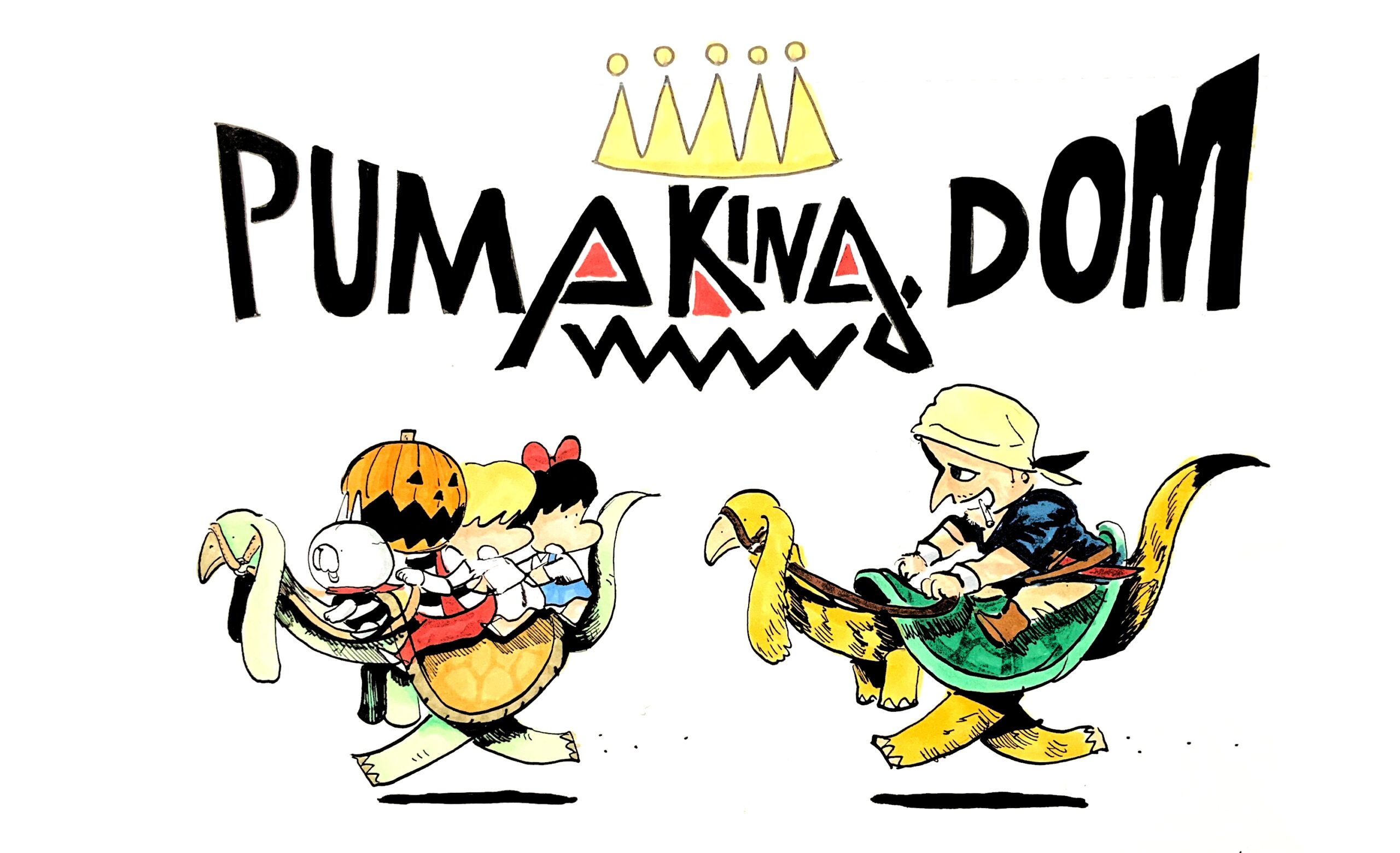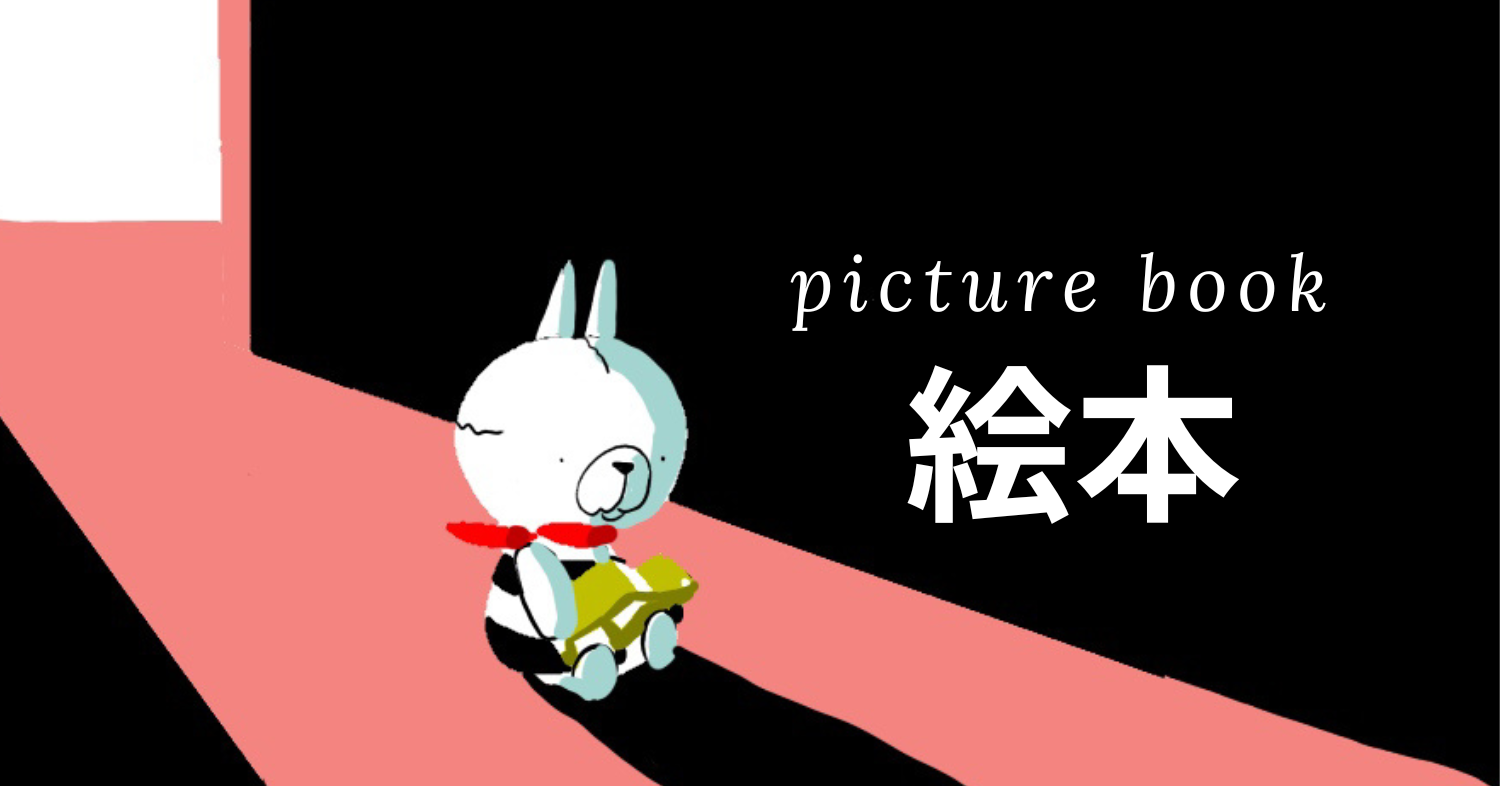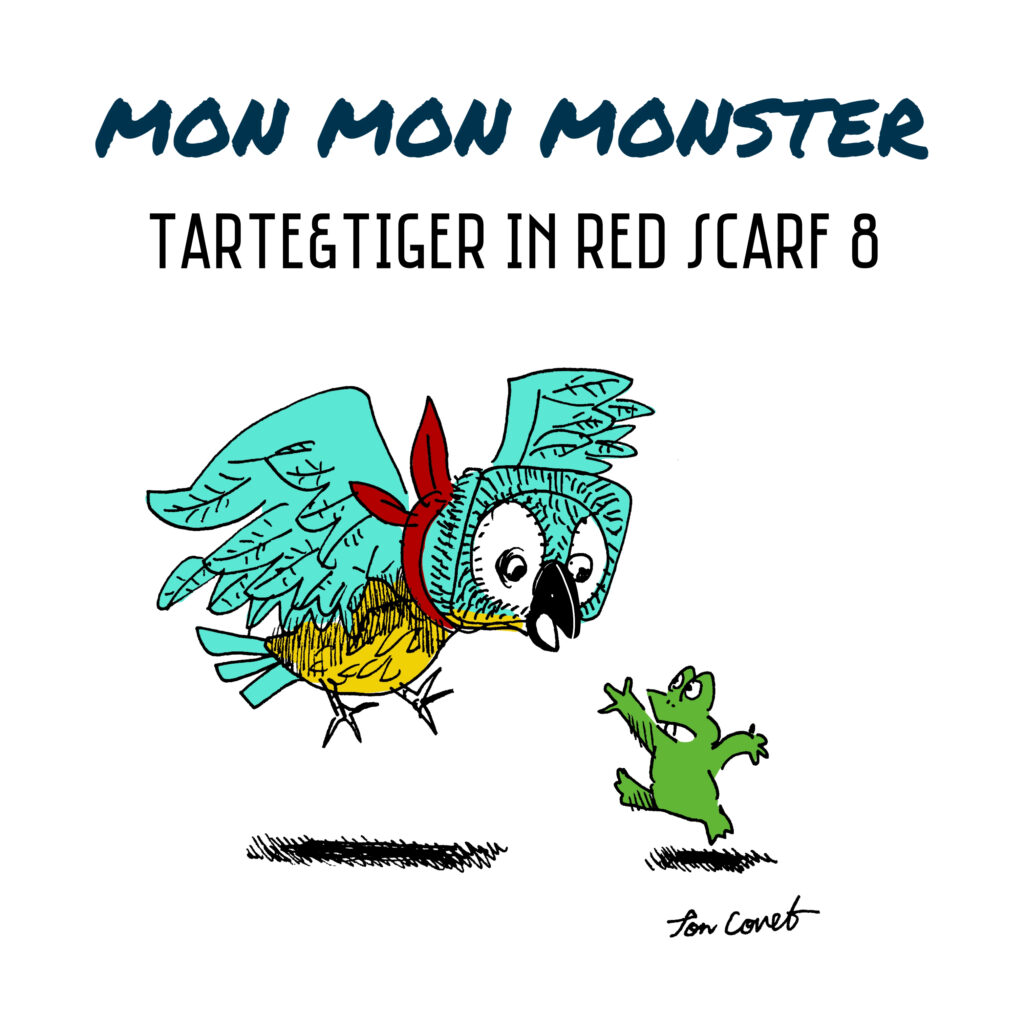その街は太陽が素通りし一年中が夜だった。
街といったが正確な大きさは誰も知らない。小さく狭いという人もいれば(人?)途方もなく広大で大きいという者もいる。とにかく誰もそんなことに興味もないしそこに太陽が登らない街がある、わかっているのはこれだけ。それで今は十分。
その街を照らすのは普段僕らが見る月とは違う雰囲気の怪しい月。月らしからぬ月。じっと見つめていると遠近感が狂い月に吸い込まれてしまいそうになる。実際人食い月という者もいる。月に大きな口があったそうだ。まったくどうかしてる。
この不思議な街の名前はスプリングウェル。あの世とこの世の近い街、そこでは死者が普通に生活をしている。異形な姿をした彼らの姿は僕らが知っているモンスターにそっくりだ。
そんな街でのお話。赤い帽子を被った骸骨の青年が何か叫んでいるところからはじまる。
第一章
「おーいタルトタルトやーい、ご飯の時間だぞ、おかしいなご飯の時間に遅れたことなんてないのに」
青年の名はトニーパスタ。愛犬のシーズーの骸骨タルトと暮らしている、心優しい青年の骸骨
「すみませんこれくらいの犬を見ませんでしたか?」
墓場の住人たちに聞いても誰もタルトのことを知りません。そんな時1匹の虫がトニーの耳もとで鳴きました。
「リーン」「虫さん何か知っているの?」
その虫はぴょんと跳ねまるでトニーにこちらに来るよう言っているようでした。
「何か知っているのかも?」トニーは虫の跡を追い森の中に入って行きました。
その森は深く危険なため入っては行けないとタルトに言い聞かせている森でしたが、言い聞かせているときにタルトが大好きなキャベツを食べていたのを思いだしちゃんと聞いていなかったかもしれないと不安になりました。
そんな心配をしながら小さな虫を見失わないように森の奥深く深く進むと虫がピタリと止まり「リンリーン」と鳴きました。そこには流れのとても強い、けして渡ろうとも思わないような大きな川が流れていました。
トニーは絶望しました、まるで100本の川を一つにしたようなその川沿いに落ちていた食べ欠けのキャベツの横で虫は鳴いていたのです。
そのキャベツに見覚えがありました。間違いありません今朝タルトにオヤツとしてあげた天狗さんの畑で取れた大きなキャベツの葉でした。
タルトは顔を隠してしまうような大きなキャベツの葉を一枚丸々手を使わずに口だけを使って食べるのが大好きでした。それは見事なもので葉がみるみるタルトの口に入っていくのをトニーは感心して見ていたものです。
トニーは思いました。ひょっとしたら葉っぱで前が見えないまま歩いて川に落ちてしまったのかもしれない。トニーは食べかけのキャベツを持ち一人立ち尽くしてしまいました。(よく見ると連れてきてくれた虫がご褒美がわりに残されたキャベツを一生懸命食べていました)
第一章終わり